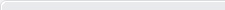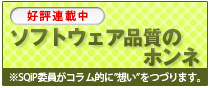2010年度(第26年度)ソフトウェア品質管理研究会の報告
鷲崎 弘宜(早稲田大学 / 国立情報学研究所)
執筆協力:阪本 太志(東芝デジタルメディアエンジニアリング(株))
◇分科会・コース: ソフトウェア品質の深堀
研究会への参加目的として、2009年度に引き続き下記の3種を主要なものとして識別しました。研究会は本来「研究」をする場として、新たな技術や考え方の発明を追求する研究型、ならびに、既存技術や知識の適用ノウハウの顕在化や体系化を追求する実践型が主要な活動といえます。しかしながら、それらの挑戦にあたっては基本的な既存技術や知識の把握が不可欠であり、ソフトウェア品質への取り組み要請の増大も相まって、調査型についても研究会の主要な活動の一つと位置付けています。
- 研究型(分科会): 新技術の発明
- 実践型(分科会): 実問題への既存技術の適用ノウハウ
- 調査型(コース): 既存技術の整理と習得
具体的には、ソフトウェア品質に関する幅広い要請に応えられるように、以下に示す研究・調査型の6分科会、ならびに、学習型の3コースを設けました(鉤括弧内は研究テーマ)。各分科会・コースが主に扱う領域をSoftware Engineering Body of Knowledge(SWEBOK、ソフトウェアエンジニアリング基礎知識体系)[3]上で整理した結果を図2に示します。いずれもソフトウェア品質を核としながら、分科会全体としてマネジメントからエンジニアリングまでの領域を広くカバーしていることを見てとれます。
| ●第1分科会 ソフトウェアプロセス評価・改善 |
| ●第2分科会 プロジェクトマネジメント |
| ●第3分科会 ソフトウェアレビュー 副主査 : 永田 敦(ソニー(株))、アドバイザ:森崎 修司(奈良先端科学技術大学院大学) -欠陥の位置と種類の特定によりレビューの効率と効果を向上-」 |
|
●第4分科会 ソフトウェア・ユーザビリティ ―エンドユーザ視点でのソフトウェア開発― 副主査 : 福山 朋子((株)インテック)、三井 英樹((株)ビジネス・アーキテクツ) |
|
●第5分科会 ソフトウェアテスト テスト仕様書の自動生成と設計作業の効率化の提案」 |
|
●第6分科会 派生開発 副主査 : 飯泉 紀子((株)日立ハイテクノロジーズ)、清水 吉男(システムクリエイツ) ●演習コースⅠ ソフトウェア工学の基礎 副主査 : 猪塚 修(横河ソリューションズ(株))、アドバイザ : 野中 誠(東洋大学) ●演習コースII ソフトウェアテスト演習コース ●特別コース ソフトウェア品質保証の基礎 |

図2: SWEBOK2004における知識領域と分科会・コースの主な対応
具体的には、2009年度に引き続いて、ニーズがあり社会要請の強い領域について研究・実践型の5分科会、ならびに、調査型の2コースを設けました。さらに、研究・実践型について、開発のあらゆる段階で有効であり、近年あらためてその重要性と難しさが再認識されつつあるレビューの分科会を新規に設けました。さらに調査型については、ソフトウェアテストの重要性が増大し学習のニーズが高まっているため、2009年度においてテスト分科会内に設けていたテスト演習コースを独立したコースとして設置し、その指導体制を強化しました。
各分科会では、参加者が抱える問題や取り組みたい技術を研究テーマとして設定し、そのテーマについて1年間かけて調査、研究、議論を重ねて最終的に成果論文の形へとまとめていきます。典型的には、各分科会で同様の問題意識を持った数名のグループが作られ、そのグループ単位で主査や副主査・アドバイザの指導・助言のもと、背景や関連技術の調査、問題の本質の把握、解決に有効な技術や考え方の考案、実験などを通じた検証、論文の執筆、成果発表会における発表とフィードバック、という具合に進めていきます。2010年度は、各分科会で上記リスト中のテーマを取り上げました。2004年度から現在までの各分科会の成果論文の内容は、研究会のWebページ[4]に公開されていますのでご一読ください(2010年度の論文は2011年3月以降公開予定)。