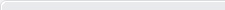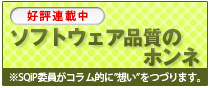モダンソフトウェアテストアカデミー:プロフェッショナルコース
~「平時のエンジニアリング」から「有事のエンジニアリング」へ~
今、世界は大きな転換期を迎えています。
その中で日本のソフトウェア技術は、高品質を叫びながら、滅んでいったガラパゴス携帯と同じような運命を辿ろうとしています。我々に何が不足していたのでしょうか?
どうも、不足を求めるすぎる考え自身が、ガラパゴスを生んだのでは無いでしょうか?
これまでの生産技術や品質システムは、安定し成熟したプロセスを求める「平時」のアプローチです。
プロセスを定義し、標準を作り、想定外のリスク=「有事」を排除するため予防を重視します。
残念なことに、計画と実績が一致することは、極めて稀であり、常に振り返り予防を補う改善を何年も続けています。
その結果、山のようなチェックリストやべからず集を残しましたが、ビジネス上成功となるゴールに近づいていますか?
ソフト開発は、原理的に「平時」と「有事」のハイブリッド型の活動です。
津波のような甚大な有事は少ないのですが、仕様変更やバグや要員のスキル不足など小さな想定外「有事」は山積です。
問題は、平時の活動(計画できる活動)と有事の活動(その場で考える活動)の比率です。平有比は、7:3から4:6位ではないでしょうか。
このように考えると、標準や知識を充実するアプローチの限界は明らかです。
過剰な平時願望が有事の対応力を弱体化し、弱体化が平時願望へフィードバックしています。
対策は「有事のエンジニアリング」を強化することです。
有事のエンジニアリングは、それほど難しいものではありません。
先ず、平時偏重の呪縛から抜けることが第一です。
例えば、バグトラッキングを考えると、モグラ叩きのシステムであることから、裏方的な扱いになっています。
有事では、スーパーモグラ叩きを考えます。
数千件の同時処理が出来るイージス艦のようなイメージです。
次に大切なことは、平時型の役割や規範に固守しない柔軟なチームワークとリーダーシップです。
有事のエンジニアリングの実装は、この柔軟な知的チームワークの構築です。
3期目に入った、本アカデミーは、このような考え方から、有事のエンジニアリングをメインテーマとし、そのリーダー的エンジニアの育成を目指します。
有事の活動が最も多い、下流工程から入り、微細な問題に流されない、全体を捉えるSynthesisの技を磨きます。
この講座は、こんなことが学べます
-
1. 考えるゼミ形式
- 基礎となる技法や分析方法について、特別な情報系の知識が無くても理解できる講義と、応用力につなぐ演習を使って進めてゆきます。
- 研修の範囲は、テストに限らず、テストの対象となる開発の方式や、システムの構成、運用、さらに技術者の組織行動など対人スキルについてもカバーします。経験の少ない未知の製品やシステムを推進する自信をもつことができます。
- 変化は、固有技術が先行するのではなく、市場ニーズから生じます。その後、いかに早く、適切な固有技術を選択し立上げを行い、最後に管理技術による維持管理へと進みます。この変化のライフサイクルに対して、それぞれの局面で必要なスキルを体系的に学びます。
- 実践力を高めるため、研修生が選んだ個別のテーマに対して分析から、他者へのプレゼンテーションまで一連の個別指導を行います。
- 少人数のゼミ形式で行い、全日を通して指導講師が個別サポートします。
- プロフェショナル教育の肝である、講師については、この分野のトップレベルの方で実務経験がある方を集めました。
- 多忙な受講生の業務を阻害しない日程構成としました。
- 合宿会場はホテルで、集中した研修を行います。
- 東京会場は、交通の便、研修環境を配慮して選定しています。
2. 変化に強いスキル獲得
3. 充実した講師
4. 日程構成
プログラム
|
ゼミ / 演習 / フィールドスタディ(課題研究) |
オリエンテーション |
【ゼミ】オリエンテーション/問題分析 |
第1月 [合宿] |
【ゼミ】開発ライフサイクルと技術の選択/システムのモデリング/(合宿)システム設計と検証・テスト技術/特論:HAYST法 |
第2月 |
【ゼミ】実装設計/実装とテスト・レビュー/検証試行設計とCFD技法 |
第3月 [合宿] |
【ゼミ】HRとマネジメント技術/リアルタイム系の設計とテスト/特論:テストライフサイクル(合宿) |
第4月 |
【ゼミ】対象システムと技術選択/対象組織と技術導入 |
第5月 |
【ゼミ】新技術の光と影/計測(メトリックス) |
発 表 会 |
【ゼミ】発表準備と最終確認発表会 |
この講座は、こんな方が対象です
- 経験を超えた変化に追従するスキルを目指す意志のある方
- 組織からプロフェッショナル候補として推薦された方
- 社内の高度人材育成や、生産技術の推進者
- 中途入社など、体系的な研修を受講できなかった中堅技術者
- 参加にあたり、ソフトウェア工学の専門知識を求めていません。
この講座の講師をご紹介いたします (順不同、敬称略)
1972年 NEC入社。周辺装置のHW開発や初期の組込み開発を経験。汎用大型機のOS開発、開発支援システム、CADなどパッケージ開発、大規模システムの問題プロジェクト支援、社内の技術研修に従事。2002年 NECを早期退職し、コンサルタント業を始める。ソニー、ヤマハ、トヨタ、フェリカネットワークス、デンソー、富士写真、松下、サムスン電子(韓国)など多くの企業にコンサルと教育を提供し多くの現場を観察。1999年明治大学兼任講師、その後、東京理科大学を経て現在、法政大学講師。 
松尾谷 徹 |
西 康晴 |
富士通(株)入社以来、基本ソフトウェア開発、ソフトウェア検査、品質保証部の業務に従事。ソフトウェア品質担当部長、特許推進担当部長などを歴任後、北陸先端科学技術大学院大学IPオペレーションセンターチーフ客員教授、特任教授を経て現職。 
堀田 文明 |
| 1985年、富士ゼロックス(株)に入社。1997年からテスト手法及びルール開発を担当。NPO法人ソフトウェアテスト技術振興協会理事。共著書に「ソフトウェアテストHAYST法入門」(日科技連出版社:「2008年度 日経品質管理文献賞受賞」)など。 
秋山 浩一 |
セミナー申し込み
日程 |
会場 |
申込 | |
| オリエンテーション | 10/12(金) | 東京 | |
| 第1月〔合宿〕 | 10/26(金)~27(土) | 熱海 | |
| 第2月 | 11/ 9(金) | 東京 | |
| 第3月〔合宿〕 | 11/30(金)~12/1(土) | 熱海 | |
| 第4月 | 12/14(金) | 東京 | |
| 第5月 | 1/11(金) | 東京 | |
| 発表会 | 2/22(金) | 東京 |
セミナーの日程、開始・終了時刻、カリキュラム、会場は、都合により変更することがあります。
また、諸般の事情によりセミナーの開催を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。
参加費
| 参加費用 | 577,500円(一般)/525,000円(会員) |
参加者の声
- 藤井 彩乃 さま((株)インテック 技術部)
<自社内の活動に自信が持てるようになりました!>
本研修は単にテスト技法を学ぶだけの研修ではありません。テスト業界を走る今のトップガンの”思い”を知りました。
また、他社の参加者や講師との議論では、異なる文化を持つ人への説明方法を常に考えさせられました。
しかし、言葉は違えどもテストによる品質改善活動という目的は同じです。1年という時間をかけて課題を見直したことによって、それまで迷いながら取り組んでいた自社内の活動(その目的や取組み自体)に、自信が持てるようになりました。
- ㈱NTTデータ 品質保証部 シニアエキスパート 岩坪 慶薫さま
<問題解決の思考プロセスにおける推進力が身に付きました!>
私は現在の実務ではテストに直接携わっていませんが、研修の範囲はソフトウェアテストに限らず、自身のフィールドスタディにも重点を置いてあるため、研修後の取組みについても常に意識しながら取り組むことができました。
多くはディスカッション形式で進行したので、問題解決の思考プロセスの訓練となり、思考の推進力も身につけることができたと思います。
職場に戻ってからの課題への取組みと、その推進力の習得、また、講師陣によるフォローが得られるため、研修後の業務への親和性が高く、非常に有意義な研修でした。
関連セミナー
- テスト技法とテストケース演習:開発技術者向け
- 効果的な受け入れテストの設計と実践セミナー
- 2日でマスターするソフトウェアテスト
- 秋山浩一のソフトウェアテスト技法ドリルセミナー
- 秋山浩一の実践!直交表、All-pair法を用いた組合せテストと状態遷移テスト修得セミナー
ツイート
問い合わせ先
教育推進部 第二課TEL:03-5378-9813
FAX:03-5378-9842
E-Mail:sqip@juse.or.jp