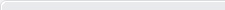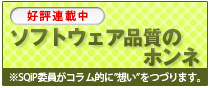ソフトウェア開発における知の整理・体系化と伝承
―JSQCソフトウェア部会「遺言」プロジェクト―
(社)日本品質管理学会ソフトウェア部会前部会長
兼子 毅
5.知識伝承の難しさ
近年の開発では、業務が細分化され、それぞれ専門性が高まってきているが、同時に「これは自分のこととは関係ない」と、他者の経験を「学ぶ」姿勢が希薄になってきている。これは想像力が欠如しただけなのかもしれないが、忙しい現代の開発者に対し、自分にとっての問題であると興味をもたせることが極めて重要である。また、体系化されていない「知」をどのように「教える」のかは極めて難しい問題で、「経験しなければ分からない」というだけでは物事の解決にはならない。
一般的な教育の理論では、新しい事柄を教えるときに、生徒側の情報処理が多ければ多いほど、定着しやすい、と言われている。目で追うよりは、声を出して読む、それよりはノートに書き写す、というように、同時に多くの情報処理が行われる方法のほうが、記憶に定着しやすいということである。最も脳を活発に使うのは「考える」ということだ。何かを教えたいと思ったときに、どうすれば生徒に「考え」させることができるか、が教える側のポイントとなる。
人材育成では、「自分で考えることができる」という目標を立てて欲しい。「考える」ためには「知識」が必要だ。家を建てる時のレンガのようなものだ。しかし、多種多様なレンガを持っていたとしても、家はできない。それらを組合せ、場合によっては加工し、手元にない場合は漆喰を固めて応急的な塊を作ることも必要だ。知識を組合せ、場合によっては仮説を立てることもあるということだ。
それらを組合せ、構造を築かなければならない。その構造がいい加減なら、すぐ崩れてしまう。論理的な思考が極めて重要、ということだ。その前に、そもそもどのような家を立てるのか、事前にイメージできていなければダメだ。言い換えれば、どのような問題を解決しようとしているのか、目的が見えていないと論理を組み立てられない。
最後のメッセージは、結局「考えろ」という言葉になった。普段の暮らしでは、あまり考えなくても済むようになっている。脳は、そのように、多くのことを習慣化して省エネ、はやりの言葉で言えばエコなのである。しかし、新しい状況や問題に直面したときには、「習慣化された行動」だけでは解決できない。その時には一気にエネルギーを投入して「考える」しかないのだ。その時には大量のエネルギーを消費するかもしれないが、良い答えを得ることができたのなら、その後はまた省エネで進むことができる。
部下に「考える癖」をつけてあげること、これが最も優れた人材育成の方針ではないか、と思う。