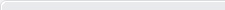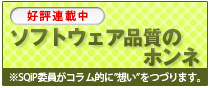論文を書くことの大切さ
株式会社システムクリエイツ
代表取締役 清水 吉男
・私と論文の接点・
復帰後、「格物 致知」ということで、手に入る文献は片っ端から入手して、毎晩仕事が終わってからアパートの部屋で夜中の2時頃まで自習しました。この状態が約3年続きます。しかしながら組織に属していないため新しい技術などで単行本になる前のものが入手できません。雑誌といっても、内容的にしっかりしたものは「bit」という雑誌ぐらいでしたので、それだけでは不足しているという不安を埋めることができません。
また、大手の企業には組織の中に先輩たちが残した知識や技術がありますし、直接話しを聞くこともできます。でもフリーで活動している者にはそうした知識や技術を手に入れることができません。時々、客先で目にしたものをお願いして借りて帰るぐらいです。今日のようなインターネットのない状況では、このハンディはとてつもなく大きなものでしたし、私自身「このままではマズイ」と「危機」を感じていました。「格物 致知」にならないのです。
この不利な状態をどうカバーするかということで、あるとき情報処理学会の論文誌を見つけ、読み始めたのです。当時は情報処理学会の会員ではなかったので、近くの書店にお願いしてオーム社から取り寄せてもらいました。その他、客先によっては電気通信学会の論文誌が置いてありました。この雑誌にもソフトウェアに関する論文が書かれていることがあり、それを見つけて借りて帰りました。これが私と論文との最初の接点です。
当時、私の回りの人でそこまでやっている人はいなかったのですが、私自身、一度躓いてこの世界から撤退しており、二度は失敗できないという状況にあったことと、復帰する際に「格物 致知」を腹に決めていたことによって、「致知」の一つの実現手段として、論文を読むというところに繫がったのでしょう。論文を手に入れて読むということには何の迷いもありませんでした。
当時、手に入る単行本は片っ端から入手して読んでいましたので、それで十分と考えることもできたかもしれませんが、復帰前に「大学」を読んでいたことで、それだけでは「致知」にならないと考えたのです。実際、まだ「そこ」に知るべき「場(領域)」があるのですから。もし事前に「大学」を読んでいなかったら、この時点で論文を読むことはなかったでしょうし、そうなると今の私はなかったと思います。
いや、自転車操業でボロボロになっていたかもしれません。実際、フリーで仕事を続けるのは決して楽なことではありません。そんな中で、「営業しない」という方針を貫くことができ、しかも一度も仕事が途切れなかったのは、やはり「格物 致知」の効果であり、そこから発した「論文を読む」という行動のお陰だったと言えるでしょう。
・論文の構成が共通していることに気がついた・
こうして論文を読んで、その構成に沿って理解した範囲で要約をまとめていました。そうして論文を読んで要約をまとめていると、論文の構成が
「abstract — まえがき — 現状分析 — 課題抽出・・・」
と共通していることに気がついたのです。
(現状分析)
・まず、現状を分析して問題を整理します。この時、データが収集されます。
・集めたデータを原因などの特徴で分類して選択しやすいように整えます。
(課題抽出)
・整理された問題から、解決の優先度が高いものや効果の大きいものを選択します。
・選択された問題を、取り組みやすいように「課題」として形を整えます。
・このとき、問題に繫がったと思われる原因の分析が行われます。
(対策の選定)
・推定されている原因に有効がありそうな技術を探したり、既存の技術を組み合わせたりします。
・この時、関連した課題を扱っている論文や文献を調べることになります。
関連しているものがあればそこでの対応方法が参考になります。
・今回の課題に適したものがなければ、それまで経験してきた中から新しい対応策を考えることになります。
(対策の選択と実施)
・そうした対応策の中から良さそうな方法を選んで、実際に取り組むためにプロセスなどの環境の整備を行い、
その上で実際に取り組みます。
(検証と考察)
・取り組んだ結果を検証し、当初の課題がどこまで解消したか検証します。
・結果のデータ計測は、事前の現状分析のときにやった方法と基本的に同じです。
・解決しなかった課題や、部分的に解決しなかった事象を確認して、継続取り組みとします。
・この時、今回の取り組みをベースに、さらに工夫して対応することになります。
さらに、この論文の構成が、まるで物事が解決していく階段のようで、読み手の私にとって心地良さ、リズムのようなもの感じたものです。同時に、この構成が問題を解決する思考のステップであり実践のステップになっていることに気付いたのです。
(このステップは、いわゆる「QCストーリー」とほぼ同じですが、当時の私にはそのような知識は持ち合わせていません。直感的にこのステップが問題を解決する、と感じたのです)