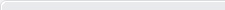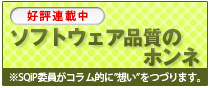2010年度(第26年度)ソフトウェア品質管理研究会の報告
鷲崎 弘宜(早稲田大学 / 国立情報学研究所)
執筆協力:阪本 太志(東芝デジタルメディアエンジニアリング(株))
ソフトウェア品質管理研究会(通称:SQiP研究会)は、主に品質の観点からソフトウェアの開発技術とマネジメント技術を研究、調査、学習、さらには交流する場として日本科学技術連盟のもとに設置され、2010年度で26年目を迎えました。4月からテーマごとに分科会に分かれてほぼ毎月のペースで定例会を持ち、約一年間にわたり活動する形態をとります。2010年度も2011年2月25日の成果発表会をもって活動を締めくくります。本稿では2010年度における一年間の研究会活動を振り返り、さらには2011年度の活動予定を紹介します。
■2010年度のテーマは「ソフトウェアと品質を考えぬく一年間」
ソフトウェア品質技術の実践にあたり、書籍やセミナーで学び後は現場の経験頼みということでは、狭い世界の自己流の域を出ません。組織標準があるといっても、それが最適と確信できることは稀でしょう。まして近年は、ネットワークや社会環境など変革の速度を増しています。一つとして同じことのないそれぞれの状況で技術を活用するには、基礎理論を習得し、エキスパートから助言を得て、同じフィールドで悩む仲間と多様な事例や視点を共有しつつ共に考え抜き、問題や解決の本質を見抜くことが重要です。
そこで2010年度の研究会では、「ソフトウェアと品質を考えぬく一年間」をテーマに掲げて、特別講義を含む様々な機会を通じた理論習得と事例把握、主査・副主査の丁寧な指導、小規模な分科会単位における密な議論と気づきの共有を通じて、「考え抜く」ことに取り組みました。「考え抜く」とはつまり、安易に最初から既存技術や書籍に答えを求めるのではなく、徹底的に「問い」や実践を重ねて問題を掘り下げたうえで、同じく問いや実践を重ねて妥当で有効な解決を個人や集団で検討することです。それらの取り組みを通じて最終的には、各参加者の個人ならびに所属先において理論や経験に裏打ちされた品質活動の実践と人材育成を目標としました。
ソフトウェア品質管理研究会は、それらの全てを提供します。研究会は25年の歴史を持ち、次の25年に向けてレビュー分科会の新設など絶えず改善し続けています。企業における品質活動の導入、発展、さらには人材育成に是非お役立てください。
■ニーズにあった研究のかたち: 調査、実践、研究
研究会には66の企業や団体から68名が参加しました。年間を通じて8回の例会を行い、さらに2010年度は2009年度に引き続き研究調査の一環として第29回SQiPシンポジウム(ソフトウェア品質シンポジウム)[1]についても参加しました。各例会では、午前中は参加者全員で特別講義を聴講し、午後はテーマ別の分科会・コースにわかれて学習や研究を行いました。特別講義は様々な知識や事例に触れて視野を広げることを目的とし、分科会・コースは特定の問題や技術について深掘りすることを目的としています。それぞれについて年間テーマに沿った事前の計画や、参加研究員の悩みやニーズに沿った柔軟な対応、さらには主査・副主査・アドバイザ・外部招聘講師による丁寧な指導により、各回のアンケート回答における満足度が高く充実した良い内容であったと評価しています。それぞれの詳細を以下に報告します。
◇特別講義: ソフトウェア品質の広がり
ソフトウェア開発の難しさの要因として、ソフトウェアが質量を有さずしばしば抽象的で自由度が高いことや、それに関連してハードウェアやネットワーク、人間・ビジネス・社会系、自然界・実世界などがソフトウェアに複雑に絡み合うことが挙げられます。そのため、従来の工業製品における開発や品質管理の考え方がそのままでは当てはまらないことがしばしばあります。そこで、人的側面、プロセスやマネジメントの側面、設計や検証などエンジニアリングの側面、さらには経済学や統計学などの広がりを知り、様々な気づきを得ていくことが重要です。
そこで2010年度の特別講義は、各分野で活躍されている方々より下記の講演をいただきました(図1参照)。ソフトウェア品質の本質について考えることの意義に始まり、メトリクスや品質管理、アジャイル開発といったマネジメント系から、プロダクトの開発におけるレビューやテストといったエンジニアリング系に至るまで幅広く、ソフトウェア工学と品質管理に関係する形で各話題が豊富な事例と共に取り上げられ、各研究員はそれぞれ多くの気づきを得ることができました。各特別講義の概要や感想は[2]より参照できます。
- 「今こそ考えよう!ソフトウェア品質」、誉田 直美(日本電気株式会社)
- 「ソフトウェアメトリクスの基礎 ~欠陥に学ぶ~」、野中 誠(東洋大学)
- 「アジャイル開発の方法論~イテレーション体験を通して~」、鷲崎 弘宜(早稲田大学/国立情報学研究所)
- 「新聞紙タワー演習」、足立 久美(株式会社デンソー)、堀田 文明(デバッグ工学研究所)
- 「Usability 2.0~ユーザビリティの現在・過去・未来~」、樽本 徹也(利用品質ラボ)
- 「レビューのすすめと進め方~レビューってなんだろう? プロジェクト・業務を乗り切るための私流レビューの進め方~」、安達 賢二(HBA)
- 「ソフトウェア開発の工業化と品質管理」、渡辺 純(富士通アプリケーションズ)
- 「Wモデルによる全体最適化」、西 康晴(電気通信大学)

図1: 特別講義の様子