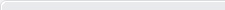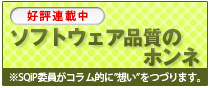「SQuBOKの利用法:参照スタイルから進化スタイルへの提案(その3)」
株式会社NTTデータMSE
ソリューションサービス事業部
コンサルティング部 堀 明広
「SQuBOK」とは「Guide to the Software Quality Body of Knowledge」の略で、正式名称は「ソフトウェア品質知識体系ガイド」です。
「SQuBOKユーザー会」は、以下を目的に2009年に設立されました。設立趣旨は以下のとおりです。
・ 先人が切り開き、培ってきた品質技術を伝承し、それらを有効利用して更には発展させるため、
SQuBOK活用の事例を共有する。また、SQuBOKをより密に活用する方策・方法を模索し共有する。
・ ソフトウェア開発に関係する者にとって、SQuBOKがより価値ある知識体系に進化し続けることに、
SQuBOKのユーザー自身も参画し、これを実現する。
SQuBOKユーザー会の詳細については以下に情報があります。SQuBOKユーザー会にはどなたでもご参加いただけますので、興味をお持ちの方は是非ご参加ください。
http://www.juse.or.jp/software/142/
【SQuBOKユーザー会 新活動の概要(前回までの振り返り)】
SQuBOKユーザー会の取り組みについて、これまで2回の記事を書いてきました。
今回の3回目の記事では具体的な取り組み方法を記していきますが、その前に,前回までを簡単に振り返っておきたいと思います。
SQuBOKには、今まで先人が切り開いてきた知見が体系的にまとめられています。
本記事の1回目では、ソフトウェア品質に関する知見は非常に広くて深淵であることを、私の実体験を交えながら紹介しました。
SQuBOKは、”樹形図”を軸にしてソフトウェア品質に関する知見が凝縮されてまとめられていますが、ソフトウェア品質に関する知見は常に進化し事例も積み重ねられて来ています。
本記事の2回目では、SQuBOKに記載されている事項を単に参照するだけでなく、ソフトウェア品質に関する知見をSQuBOKユーザー会のメンバー達で集約・共有化していくことを提案しました。
・新たに出された知見を整理し体系付けるのに、SQuBOKを軸として利用する。
・勉強会等で出された意見等を、その場限りでなく一個の体系に記録し、蓄えていく。
・それらを使って更に議論を深めていき、新たな知見を産み出していく。
具体的には、ソフトウェア品質に関わる「書籍」「論文」「記事」「規格」「トピック」をまとめていきたいと考えています。
●書籍
SQuBOKのその名は「ソフトウェア品質知識体系ガイド」です。
SQuBOKの本文中に記載されているものはその事項に関する要約であるため、その中身について、より理解を深めるためには、「参考文献」をあたる必要があります。
SQuBOKの「参考文献」には、その記載量の制限から厳選されていますが、「参考文献」でポイントされていないものにも、良書はたくさんあります。また、SQuBOKが出版されて以降にもソフトウェア品質に関わる多数の書籍が出版されています。更に視野を広げ、ソフトウェア品質に直接的に関連しないものにも参考にすべき書籍は非常に多く、これらを紹介し合うことには、大きな意義があると思います。
●論文
今回提案している中で、一番重視したいのは、この「論文」です。
論文と言うと、何か堅苦しいとか、敷居が高いイメージなどがあるためか、論文を読んだことが無いエンジニアが多いように思います。まったくもったいない話です。どうか食わず嫌いをせず、一度論文を読んでみることを強くお勧めします。
例えば、日本科学技術連盟主催の「ソフトウェア品質シンポジウム(通称:SQiPシンポジウム)、ASTER主催の「ソフトウェアテストシンポジウム(通称:JaSST)」では、実務者が執筆した事例報告が数多く報告されています。
これら論文では、その組織やプロジェクトで抱えている問題・課題を整理し、それを解決するための方法を考察してそれを実施し、その結果がどうだったのか検証するまで分かりやすく整理されており、書籍等だけは得られにくい実践事例を知ることができます。
「為すべきことは分かっているが、具体的にはどう手をつけていけば良いのか分からない」といったケースや、「取り組みはしているが、壁に当たって行き詰まり・手詰まりし、悩んでいる」方も多いかもしれません。こういった時には、論文でヒントになる事柄が見つかることが多いものです。
また、論文を読むことで、各組織ではどんな取り組みがなされているか、トレンドも把握でき、視野を広げることにも役立ちます。
しかし、どこで、どんな論文が発表されているか、その入手方法が分からない方も多いことでしょう。
これらをSQuBOKの樹形図を軸にして整理し、それらの情報を共有したいと考えています。
書籍を紹介する際には、単に書籍名・著者・出版年月等のデータだけではなく、紹介者による感想や内容に関する意見も含めておくと議論もしやすくなると思います。
●記事
ここで言う「記事」とは、技術情報誌やビジネス誌、新聞・ニュースの記事、これらに関連するinternetサイト、webマガジン、blog等を指しています。 ソフトウェア品質に関する調査は、書籍や論文だけでなく、上述の「記事」を検索サイトで調べることも頻繁に行いますが、改めて言うまでもなく、各種メディアやinternet上の情報は爆発的に増加してきているため、目的の情報を得ることが難しくなってきています。
こういった情報を抽出・整理・共有すると、知見の発掘・整理に大いに役立つと考えています。
●規格
SQuBOKの出版後にも、ISO・IEC・IEEE・JIS等の規格は新規策定・改訂・廃止がなされています。現状に合わせて状況を俯瞰・整理することを考えています。
また、ソフトウェア品質の観点で、その規格で記載されている内容の意図、複数の規格の関連・相違点などが議論できると良いと思います。
●トピック
私自身の感触ですが、ソフトウェア品質に関わるエンジニアは、組織の垣根を越えた交流が盛んで、横の繋がりが強いように思います。例えば、SQiPコミュニティやソフトウェアテスト技術者交流会等のコミュニティを母体に、各地域で自主的に活発に勉強会等が催されています。私自身このような勉強会や研究会活動をこれまで一生懸命にやってきましたが、その過程で多くの方々に育てていただいたと思っています。
こういった活動の存在そのものを紹介し合うこと、また、そこでディスカッションで交わされた意見や得られた知見、整理された事項等を持ち寄って蓄積・共有することが出来れば互いに大きなメリットになると思っています。
また、これらの情報共有をする過程で、互いに持ち寄った情報に対して意見・補足情報等を加えるようにしていったら、別の議論が生まれ、それが新たな知見の創出に繋がるものと思っています。