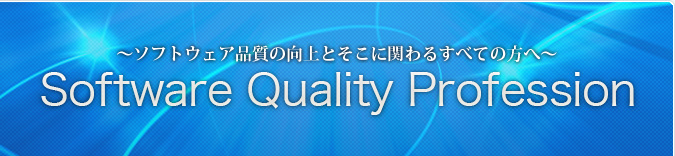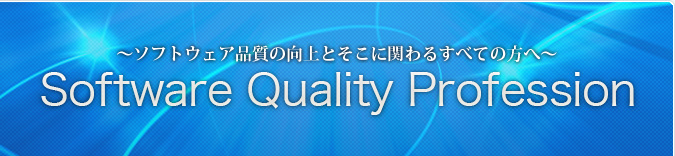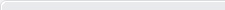ソフトウェア品質技術の領域を拡大し、適用する一年
ソフトウェア品質技術の実践にあたり、人材育成が重要なことはいうまでもありません。しかし、ソフトウェアはインターネットや社会環境など変革の速い領域ですから、各企業で独自に教育コースを設け、適切なOJT を実施することが、非常に困難となっています。
ソフトウェア品質管理研究会では、ソフトウェア技術の変化に追随し、2011 年度以来「形式手法と仕様記述」「ユーザーエクスペリエンス(UX)」「メトリクス演習コース」「リーダシップとモチベーション」「欠陥エンジニアリング」といった分科会を拡充し続けてきております。
指導陣には、経験豊富で、第一線で活躍中の、研究者、実務者、コンサルタントを主査・副主査に置き、最先端の専門的知識により適切で丁寧な指導を行います。
また、小規模な分科会単位での密な議論と合宿や臨時会などを通して、社外の人と触れ合い意見交換することで、自らの活動を振り返り、今後の技術者としての方向性を得るとともに、信頼できる社外の仲間を作ることも期待できます。
昨年度の30 周年という節目を経て、(1)研究成果の質の向上、(2)習得スキルの実務適用、という2つの方向性で本研究会の更なる発展を推し進めています。
(1)を目指す研究員については、SQiPシンポジウムは元より、他の学会への論文投稿などのチャレンジもサポートします。(2)を志す研究員については、1年間の活動終了後でも実務適用した経験を気軽な形で共有できる場を設け、当研究会卒業後も刺激を与え合うような関係性を維持する仕掛けを作ります。
幅広い内容のコースを用意しておりますので、初学者の教育や職場の将来を担うリーダーの育成などに本研究会を活用して頂ければ幸いです。
|

第31年度ソフトウェア品質管理研究会
運営小委員会委員長 小池 利和
(ヤマハ(株)
品質保証部 DMI品質保証室 品質管理G)
|