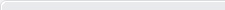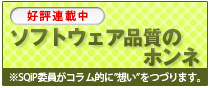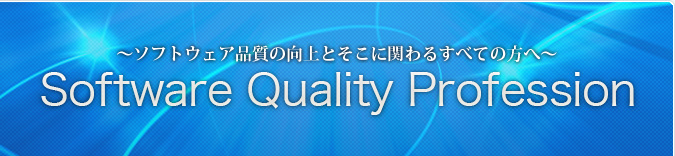
分科会概要
このようなことでお悩みの方には、特におすすめです!!
|
等々お悩みの方は 第1分科会 「ソフトウェアプロセス評価・改善」 をおすすめいたします! | ||
|
等々お悩みの方は 第2分科会 「リーダーシップとモチベーション」 をおすすめいたします! | ||
|
等々お悩みの方は 第3分科会 「ソフトウェアレビュー」 をおすすめいたします! | ||
|
等々お悩みの方は 第4分科会 「ユーザエクスペリエンス(UX)」 をおすすめいたします! | ||
|
等々お悩みの方は 第5分科会 「ソフトウェアテスト」 をおすすめいたします! | ||
|
等々お悩みの方は 第6分科会 「派生開発」 をおすすめいたします! | ||
|
等々お悩みの方は 第7分科会 「欠陥エンジニアリング」 をおすすめいたします! | ||
|
等々お悩みの方は 演習コースI 「ソフトウェア工学の基礎」 をおすすめいたします! | ||
|
等々お悩みの方は 演習コースII 「形式手法と仕様記述」 をおすすめいたします! | ||
|
等々お悩みの方は 演習コースIII 「ソフトウェアメトリクス」 をおすすめいたします! | ||
|
等々お悩みの方は 特別コース 「ソフトウェア品質保証の基礎」 をおすすめいたします! |
第1分科会 ソフトウェアプロセス評価・改善 |
主査 : 三浦 邦彦(矢崎総業(株))
|
(1) |
メンバーが希望する分野、課題、テーマに応じてサブグループを作る。 |
(2) |
サブグループごとに、メンバーからリーダーを選定し、そのリーダーシップのもと、メンバー主体による運営活動(研究テーマ・目標の決定から研究作業に至るまで)を行う。 |
(3) |
主査・副主査は、基礎的な考え方、手法や方法論、最新情報、事例などを紹介し、研究を進めていくための助言と支援を行う。 |
3. 各回の活動概要
第1回 (5月)
- 分科会の主旨・目標の説明
- メンバーの自己紹介および質疑応答(担当業務、希望する研究テーマ)
- リーダー選出、グループ化の検討
- 研究テーマと研究目標についての検討
第2回 (6月)
- 研究テーマと研究目標についての検討および決定
- 今後の進行に向けて作業項目の洗い出しと分担の決定
第3回 (7月:合宿)、第4回 (10月)、第5回 (11月)、および(必要に応じて)臨時会
- 調査研究報告と討論の積み重ねによる共同研究の推進
第6回 (12月)
- 研究結果のまとめ
- 報告書の内容構成と執筆分担の決定
第7回 (1月)
- 研究報告書のレビューと研究発表の準備・練習(PPT作成他)
第8回 (2月)
- 研究成果発表会
第2分科会 リーダーシップとモチベーション |
主査 : 早川 勲(アズビル(株))
|
||
第3分科会 ソフトウェアレビュー |
主査 : 中谷 一樹(TIS (株))
|
(1) | 研究生がレビューに関して抱えている問題・課題を出し合う |
(2) | 研究生全員で課題を共有し解決したいテーマを決定する |
(3) | 希望するテーマに応じてサブグループを作る |
(4) | 研究生主体でチーム運営を行う(サブグループごとのリーダは立てない) |
(5) | 主査・副主査は、基礎的な考え方、手法や方法論、最新情報、事例 |
第4分科会 ユーザエクスペリエンス(UX) |
主査 : 金山 豊浩((株)ミツエーリンクス)
|
||
第5分科会 ソフトウェアテスト |
主査 : 奥村 有紀子((有)デバッグ工学研究所)
|
||
第6分科会 派生開発 |
主査: 飯泉 紀子((株)日立ハイテクノロジーズ)
|
||
第7分科会 欠陥エンジニアリング |
主査 : 細川 宣啓(日本アイ・ビー・エム(株))
|
||
演習コースI ソフトウェア工学の基礎 |
主査 : 鷲崎 弘宜(早稲田大学)
|
||
演習コースII 形式手法と仕様記述 |
主査: 栗田 太郎(ソニー(株))
|
||
演習コースIII ソフトウェアメトリクス |
主査: 小池 利和(ヤマハ(株))
|
||
特別コース ソフトウェア品質保証の基礎 |
主査 : 相澤 武((株)インテック)
|
| 回 | テーマ | 内容 |
| 1 | ソフトウェアの品質管理概論 | ソフトウェア品質管理の概要として、ソフトウェア品質の捉え方、品質管理のポイント等について説明する。 |
| 2 | 品質マネジメントシステム | ISO9001 やCMM / CMMI 等ソフトウェアの品質マネジメントシステムについて説明する。 |
| 3 | ソフトウェア生産管理技術(プロジェクト管理技術) | ソフトウェア生産におけるQCD の管理手法や技術について説明する。 |
| 4 | 品質改善/改革技法 | 品質の改善/改革を進める上でのポイントや狙いどころ、技術等について説明する。 |
| 5 | 品質データ分析技術 | 品質データの分析技法(統計手法等)や品質データの収集/分析/評価の事例等について説明する。 |
| 6 | レビュー技術 | デザインレビューのポイント、技術、進め方等について説明する。 |
| 7 | テスト技術 | テスト項目設計技法、テスト実施のポイント等について説明する。 |
| 8 | 組込みソフトにおける品質保証 | 携帯端末、情報家電、車載機器等組み込みソフト領域が急拡大していることを踏まえ、その特性を踏まえた品質保証のポイントを説明する。 |
| 9 | ソフトウェア品質管理の実際 | 代表企業におけるソフトウェア品質管理の事例を発表し、各種技術が実際にどのように適用されているかを習得する。 |
| 10 | まとめ |