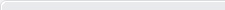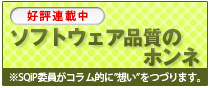論文を書くことの大切さ(2)
株式会社システムクリエイツ
代表取締役 清水 吉男
◆ MLを介して活発な意見の交換 ◆
SQiP研究会の分科会の活動は、月に1回程度の定例会があり、そこでは顔を合わせての議論ができますが、普段はML(メーリングリスト)を介しての議論になります。論文作成の詰めの段階になるとチームで1日に50通前後の添付ファイルを伴ったメールが飛び交います。これをレールから外れていないかチェックするだけでも大変です。ただし、MLでの議論に慣れていない人は,最初は戸惑うようです。
直接、顔を合わせての議論は、慣れていることもあってやりやすいようです。自分の考えの表現の仕方によって論点が外れる兆しが見えたときは、その場で表現し直すことができます。何よりも、メンバーの意見を聞きながら考えを整理し修正することもできます。
MLではこうはいきません。お互いの表情は見えませんので、文章での表現がキツくなったり、正面から反論されたりするとカチンときたり、落ち込んだりするかもしれません。でも、ここで冷静に対応することを覚えます。また、Aさんのメールに対してBさんとCさんがそれぞれの意見を同時に返信することも起きます。そのような場合は調整には余分な時間が必要になります。
でもMLだからできることもあります。それまで発信された意見はすべて文字の形で手元に残っていますので、メールを読み直して真意を汲み取ったり、メールをさかのぼって相手の考えの流れを確認したりすることもできます。何よりも、相手の文章をしっかり読み込んで、その上で自分の意見をきちんと文章にしてから発信することができます。
このようにMLを使っての議論には一長一短ありますが、これをうまく使いこなすことは、これからの研究活動には重要な手段になりますので、SQiP分科会の活動を通じて、これに慣れていくことは役に立つはずです。
◆ 論文を書くことを通じて得るもの ◆
「分科会」は、最終成果物として「論文」の形にまとめることになっています。ところが、ほとんどの人は会社に入ってから論文というものを書いていないと思います。研究職に就いていないかぎり、業務のなかで論文を書く機会はないでしょう。
初めてSQiP研究会に参加する人のなかには、ここに来ると自分の回りの問題の解決方法(解答)がもらえると思っている人はいますが、最初は困惑することでしょう。自分で身の回りにある問題を集めてきて、それを何らかのキーワードで分析し、そこから取り組む課題を抽出して解決策を考える・・・。という作業に取り掛かるなかで、分科会の活動の意味がわかってくるようです。
SQiP研究会分科会の活動のなかで手に入れるのは、「論文的思考」を使って問題を解決する方法です。もちろん、現実の問題を解決する方法は手に入るのですが、取り組みのテーマはメンバーの「共通項」になるため、それぞれの人にとって解決したいことの一部分にならざるをえません。
それでも、問題を解決するための思考や取り組み方は手に入ります。これらは汎用の技術であり、これを手に入れておけば、いつでも応用できるものです。これこそがソフトウエア技術者として生きていくための重要な汎用技術なのです。現実に、このような技術を身につける機会は、SQiP研究会の分科会以外にはほとんどないでしょう。
(論文を書くことの効果については「Quality One 8月号」で述べましたので,ここでは省略します.)