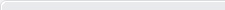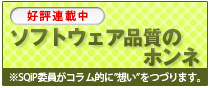論文を書くことの大切さ(2)
株式会社システムクリエイツ
代表取締役 清水 吉男
◆ 分科会を通じての友人 ◆
分科会の活動のなかで、課題の整理から問題の解決方法、さらには論文の作成にわたって、分科会のメンバーは休日も関係なく毎日夜遅くまでメールで意見をぶつけ合います。そこでは、お互いの性格や考え方を意識しながら自分の意見をぶつけていきますが、それでも意見の違いが表面化することがあります。
実際、自分の考えに対して「いや,私はむしろこう考える」と真正面からボールが返って来ることがあります。日本人は職場で意見をぶつけ合うといった経験が少なく、多くの人はこの場面で戸惑うようです。
職場のなかであれば、単に「考えが合わない人」として対応すれば済むのですが、一つのテーマで研究活動をするメンバーとなればそうはいきません。自分の考えの方が優れていると思う時は、相手を説得する方法を考えたり、メールを読み返して妥協できるところを探がしたりします。
「論文」という形にすることが課せられている状況では、ここを避けて通ることはできません。そうして彼らは一回りも二回りも成長するのです。そうして、みんなでゴールテープを切ったとき、彼らは「チーム」から「クルー」に変わるのです。SQiP研究会の分科会活動が終了しても、このクルーのメンバーはこの先も交流が続くはずです。なかには個人的に協同で研究活動を続けることも考えられます。
◆ 第4のProfessionへ ◆
SQiPは「Software Quality Profession」の略ですが、この「Profession」はただの「専門家」という意味ではありません。聖職者、医者、法律家の3種類の専門家を指します。つまりそれぞれの領域での高い専門技術の他に、強固な倫理観を求められているのです。そこにソフトウエアの(品質)技術者も参加できるように、というのがSQiPの理念です。
でも、知識や技術が不十分では、倫理観や職業観を維持するのは容易ではありません。このことは、過去においていろいろな領域での専門家が犯した過ちからもわかることです。
私が40年前にこの世界に戻ってくるときに、日々の行動指針として「大学」から引用した「格物 致知 誠意 正心」は、SQiPが目指す「Profession」と通じるところがあると思っています。
そして、この分科会の活動のなかで、彼らはその階段を登ることになるのです。
(「格物 致知 誠意 正心」については8月号をご覧ください)