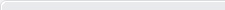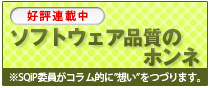すべてのソフトウェア開発者におくる:ソフトウェア品質シンポジウム2011
株式会社東芝
小笠原 秀人
チュートリアル
今年のチュートリアルは、下記のテーマでした。
「基礎から学ぶソフトウェア品質マネジメント」
河合 清博氏 (一般社団法人 情報サービス産業協会)
このチュートリアルは、ソフトウェア品質管理の基本を学ぶことを目的として毎年提供しています。ソフトウェア品質管理の業務を初めて担当する方や、基本を理解して自分たちの活動に活かしたいという方にお勧めです。来年以降も継続して実施する予定ですので、ぜひ活用してください。
産学連携セッション
今年度から産学の連携を深めるために、申込み方法として「学生枠」を設けました。さらに、若手研究者を招待し、「ソフトウェア品質に対する産学連携研究の明日を語る」というテーマで議論するセッションを開催しました。このセッションへの参加者はそれほど多くはなかったのですが、産学の両方からの意見を交わすことができ、次につながる議論になったと好評でした。来年度以降も、産学連携の試みは継続していきたいと思います。このセッションの概要を以下に示します。
コーディネータ: 野中 誠 氏(東洋大学経営学部 准教授)
http://www.se.mng.toyo.ac.jp/
目的:
このセッションでは、産学連携研究に関心をもつ若手研究者と実務者を招いて、ソフトウェア品質に関するこれからの産学連携研究の可能性を探りました。若手研究者はどのような研究テーマに関心を持っているのか、産学連携研究にどのような可能性を見いだしているのか。一方、実務者は、アカデミアとの共同研究にどのようなメリットを期待しているのか。そして、SQiP という場は、産学連携研究にどのような貢献ができるのか…。これらのトピックについて、ざっくばらんな座談会形式で話を進めました。
参加した若手研究者(敬称略、50音順):
天嵜 聡介 氏(岡山県立大学情報工学部情報システム工学科 助教)
「工数見積もり手法に関する研究、ソフトウェアの品質予測に関する研究」
http://peter.cse.oka-pu.ac.jp/s-amasaki/
阿萬 裕久 氏(愛媛大学大学院理工学研究科電子情報工学専攻 講師)
「ソフトウェアメトリクス、エンピリカルソフトウェア工学に関する研究」
http://www.hpc.cs.ehime-u.ac.jp/~aman/
石尾 隆 氏(大阪大学情報科学研究科コンピュータサイエンス専攻 助教)
「ソフトウェア保守、プログラムスライシング、動的解析に関する研究」
http://sel.ist.osaka-u.ac.jp/~ishio/
小林 隆志 氏(名古屋大学大学院情報科学研究科情報システム学専攻 准教授)
「ソフトウェア再利用、ソフトウェア理解、データ工学応用に関する研究」
http://www.agusa.i.is.nagoya-u.ac.jp/person/tkobaya/index.html
鷲崎 弘宜 氏(早稲田大学基幹理工学部情報理工学科 准教授)
「再利用と品質保証を中心としたソフトウェア工学に関する研究」
http://www.washi.cs.waseda.ac.jp/
SIG
SIG(Special Interest Group)は、テーマごとに各自で抱えている悩みや課題についてざっくばらんに情報・意見交換を行う場です。シンポジウムでは、「見る・聴く・話す・考える」をポイントの一つとしています。参加者はただ聴くだけでなく、参加者同士で情報・意見交換し伴に考えることを狙いとしています。今年度は、下記11のテーマで実施しました。
テーマ1: 「ソフトウェア製品の品質保証 -品質保証部への期待と現状-」
テーマ2: 「ソフトウェア品質保証の普及と啓蒙」
テーマ3: 「プロセス改善の進め方」
テーマ4: 「派生開発でどうやってQCDを達成するか -プロセスと仕様変更の両面から考えよう-」
テーマ5: 「『テストの壁』をぶち破れ!」
テーマ6: 「あのレビューのプロに聞いてみよう!」
テーマ7: 「コーチングで本当のやる気を引きだそう」
テーマ8: 「人材育成 ~“開発者が自らを育成したくなる環境作り”について考えよう!」
テーマ9: 「測りにくいものを、どう測る?」
テーマ10:「見つめ直してみますか? 自社の品質向上策」
テーマ11:「JCSQE中級資格者の集い」
SIGの企画・運営につきましては、ソフトウェア技術者ネットワーク(S-open)、高品質ソフトウェア技術交流会(QuaSTom)、ソフトウェア品質管理研究会(SQiP研究会)のコミュニティ、研究会にご協力をいただきました。ありがとうございました。
特別講演
「日本の宇宙開発最前線を語る ―日本の基幹ロケットH-IIA/H-IIBについて―」
前村 孝志氏(有人宇宙システム(株))
打ち上げ責任者をされている有人宇宙システムの前村 孝志氏にご登壇願いました。失敗を全く許されないロケットの開発において、どうやって高い品質を維持し、それを伝えているのかというところを話していただきました。打ち上げのビデオから始まり、“ロケットのソフトウェアはC言語で5万行です。だいたい、自動販売機程度の規模ですね”、というユーモアを持ちながら、品質についての話しは、非常に泥臭いものでした。準備作業を一つ一つ確認し、手順書を読み合わせ、見える形で確認させる。机上シミュレーションを徹底させ、Know-how、know-why、 チェックリストを作っていく。変えたところを徹底的に検証する。人が変わった時は、以前やっていた人、初期の開発者、OBを呼んでレビューしてもらう。それでもある想定外のことを考えていくことは、最終的に人に依存し、何人もの人に何重にチェックしていく以外はない。“打ち上げは妥協を許さない取り組みであり、真剣勝負である”という言葉に重みを感じました。“ソフトウェアは、ハードウエアをとおして実際どうなるのか、現実とのバランスをとる必要がある”、“品質に対して情念をもて”、“何かあった時には、本気でやっていくことを自ら動いて相手に伝える”など、非常にわかりやすい説明、穏やかな口調の中に、品質に対する強い情熱を感じました。そして9月23日に、H-IIAロケット19号機の打ち上げが無事成功しました。おめでとうございます。